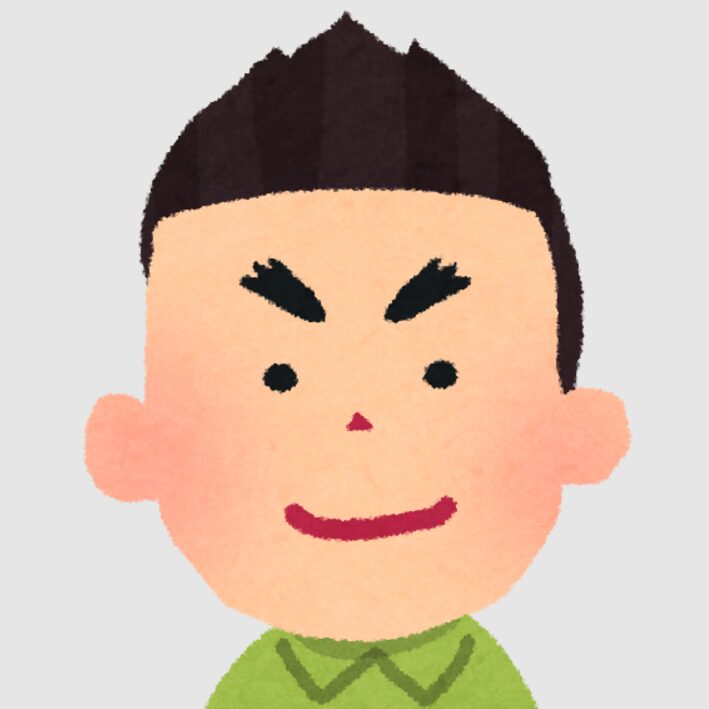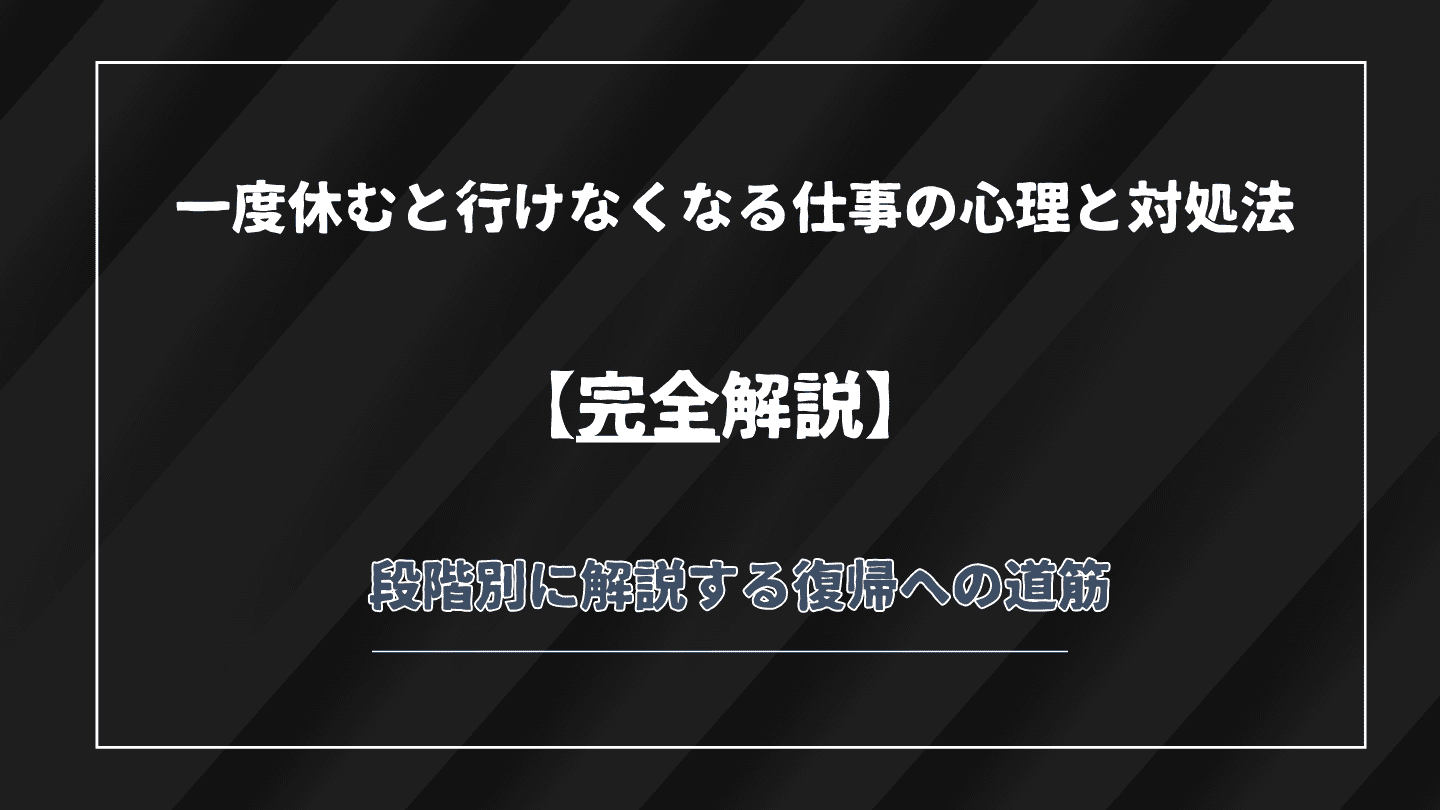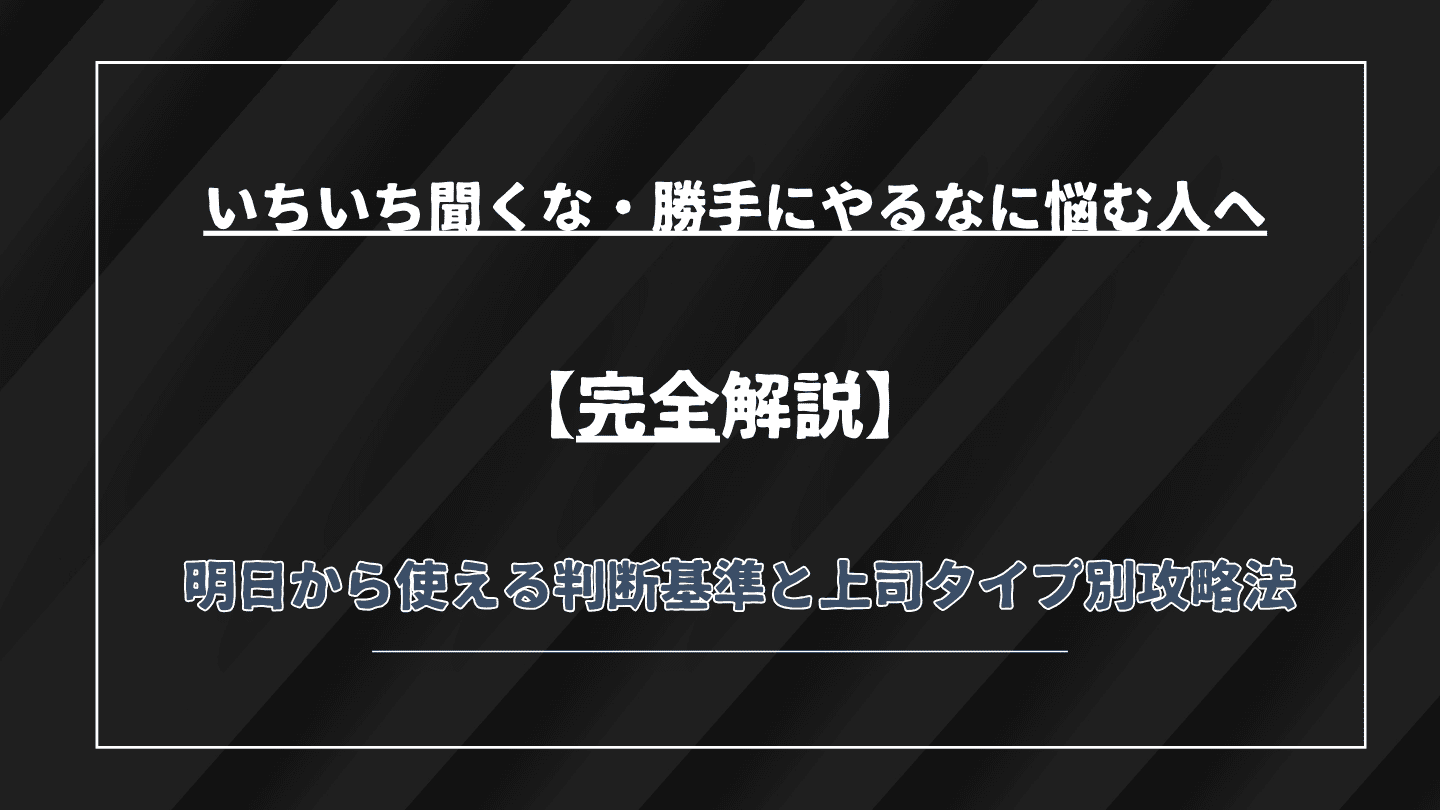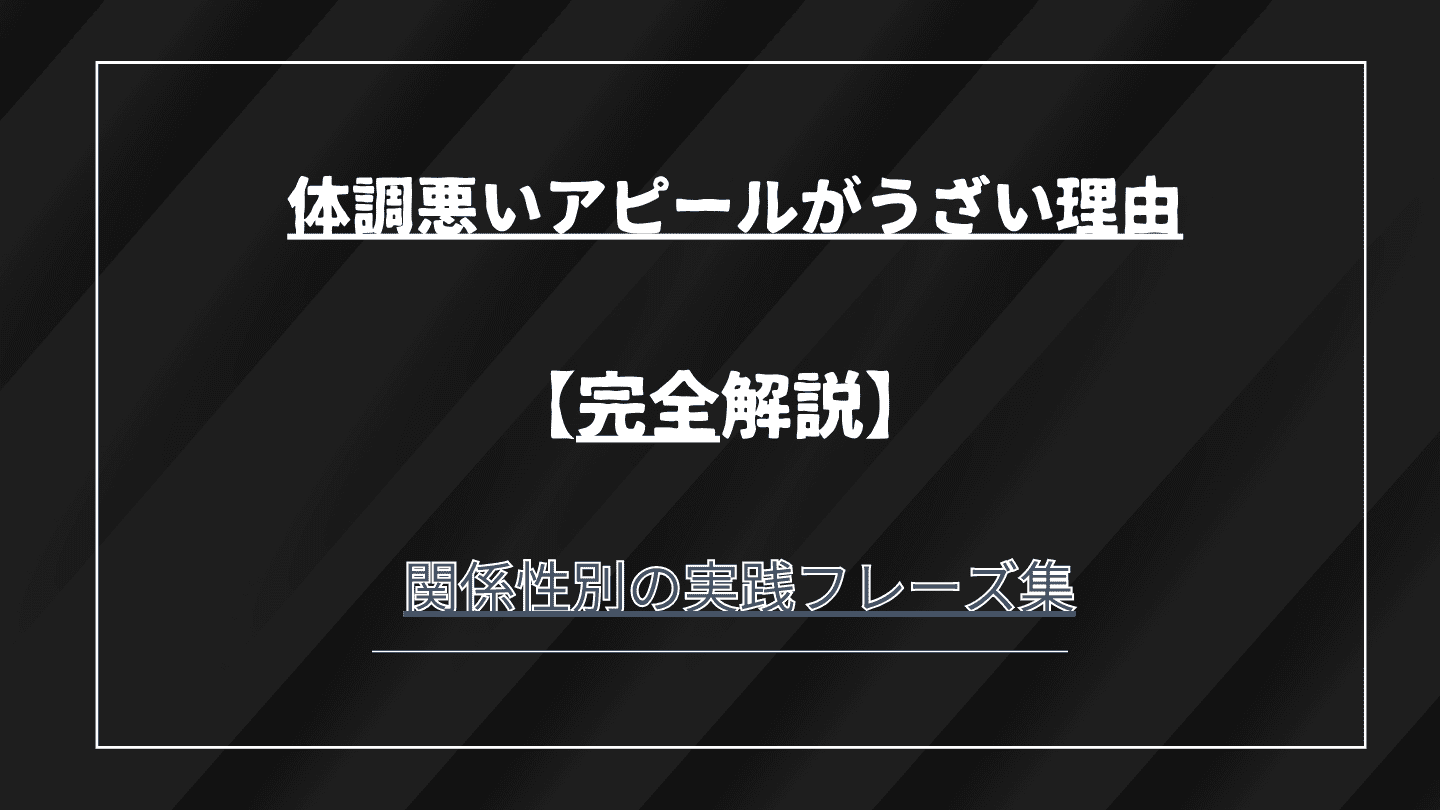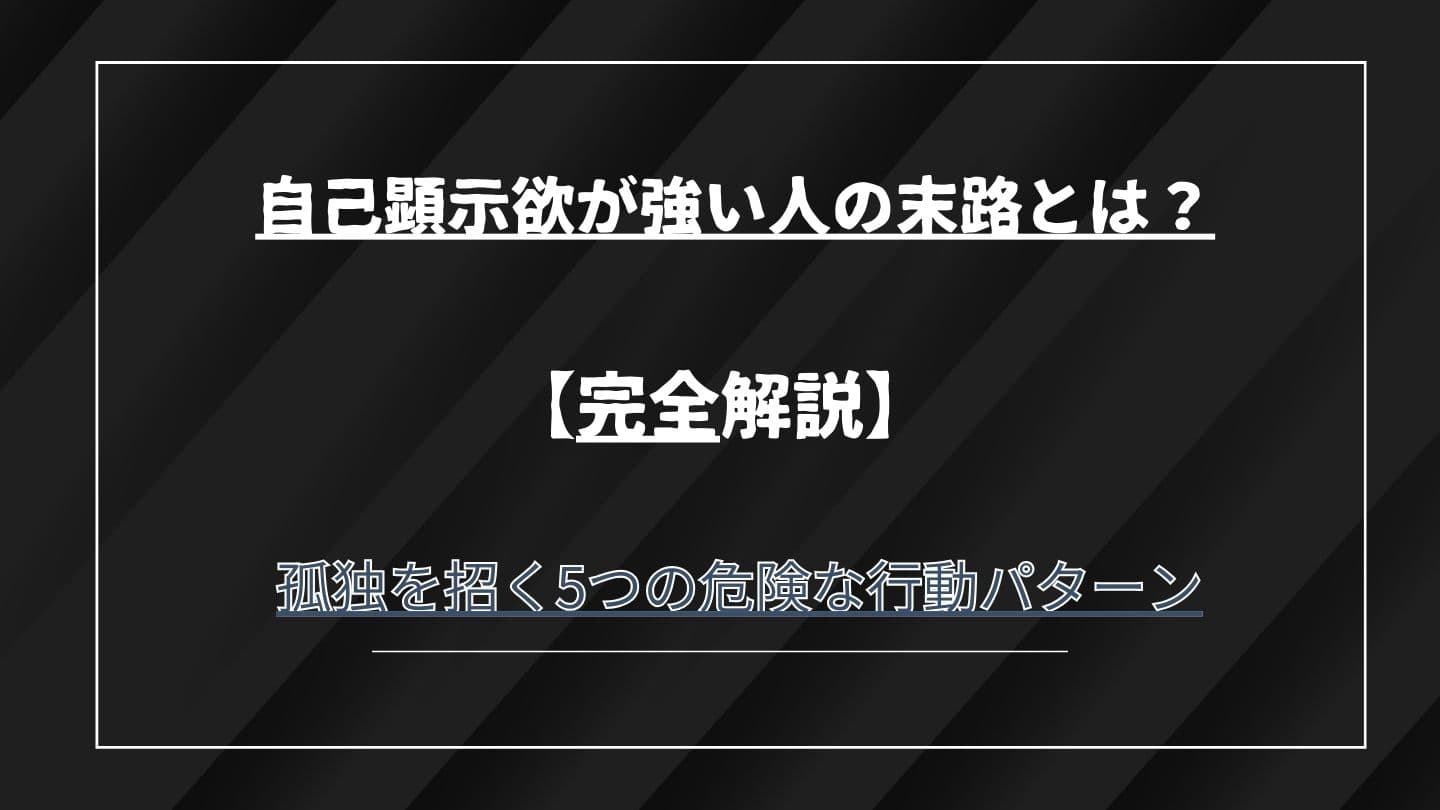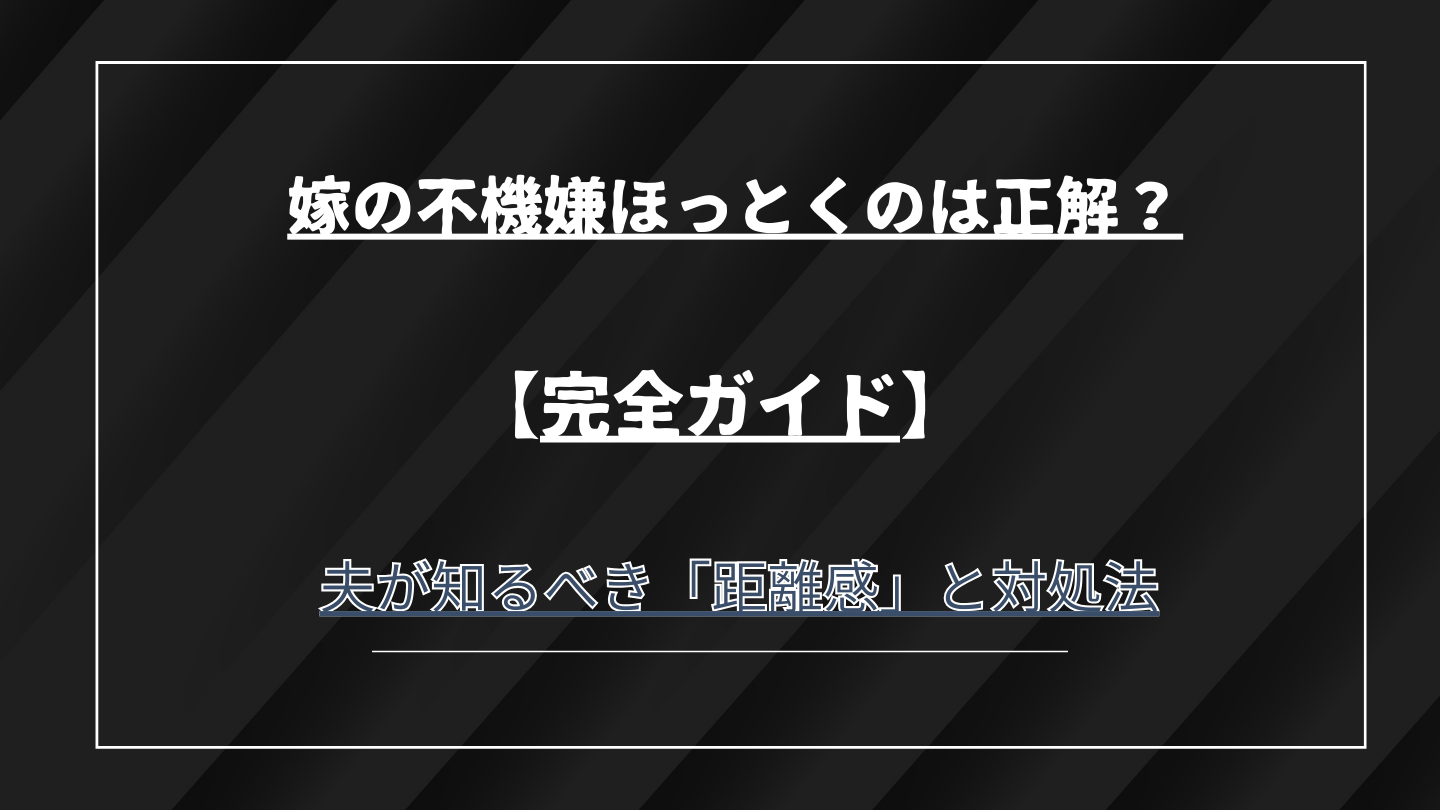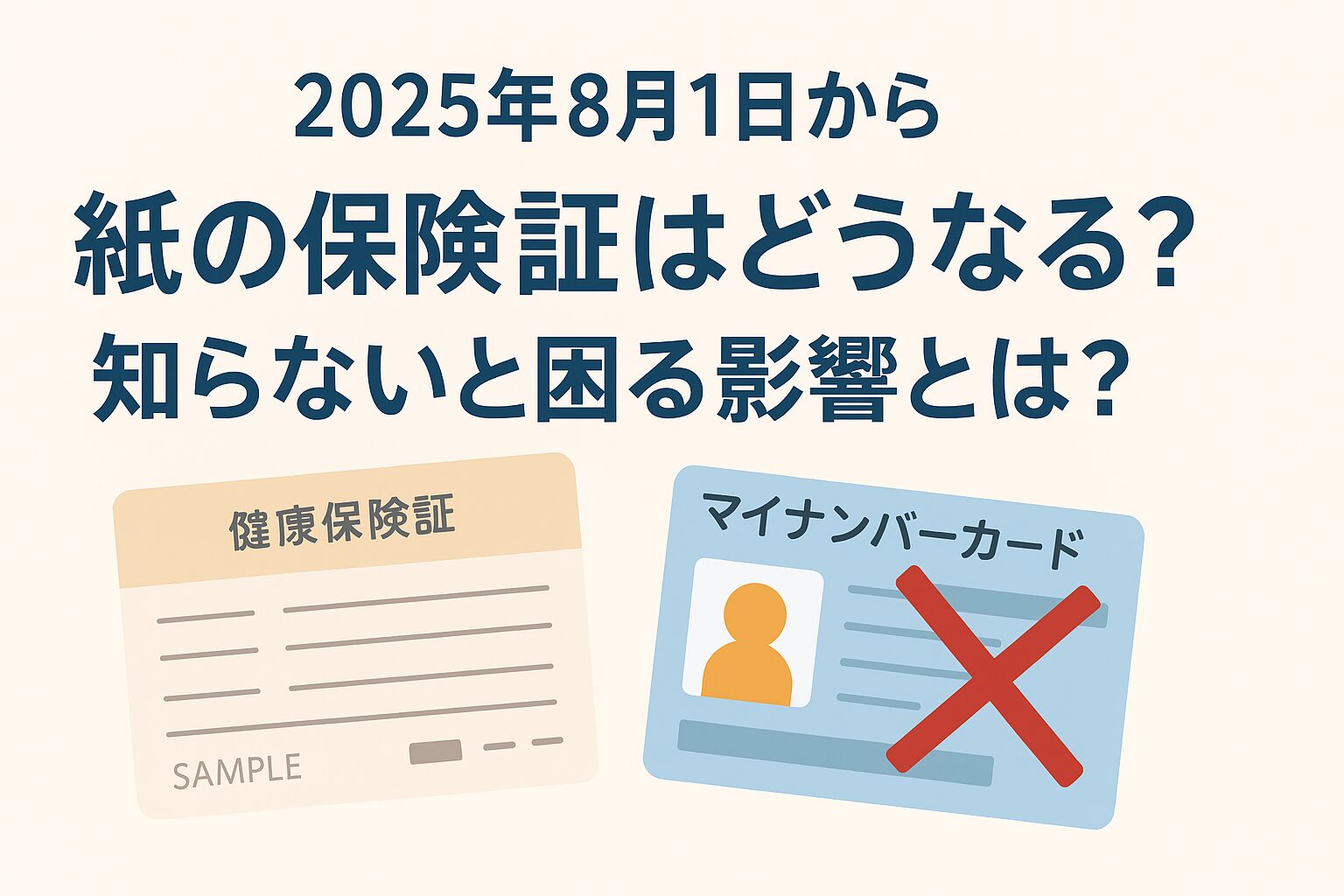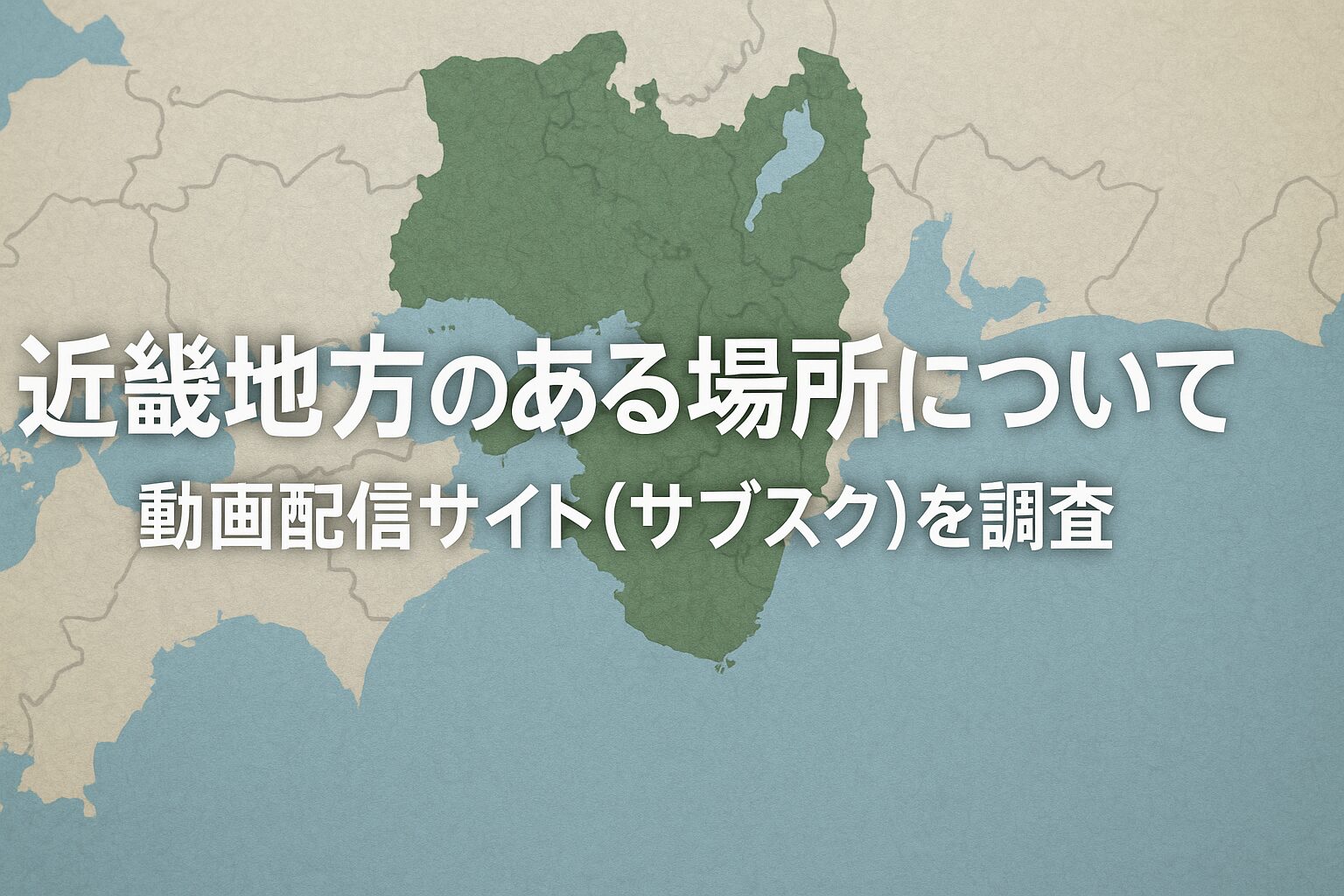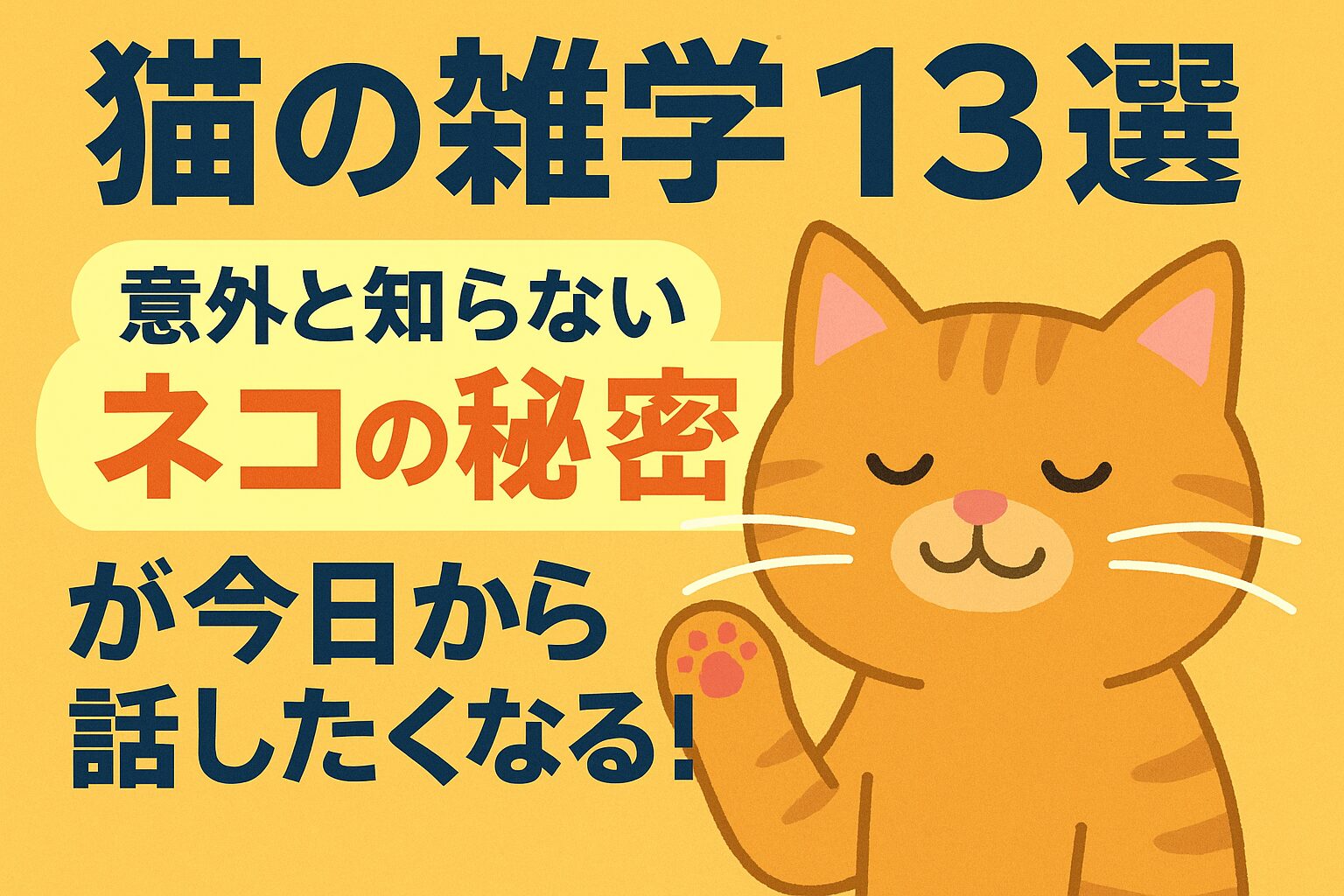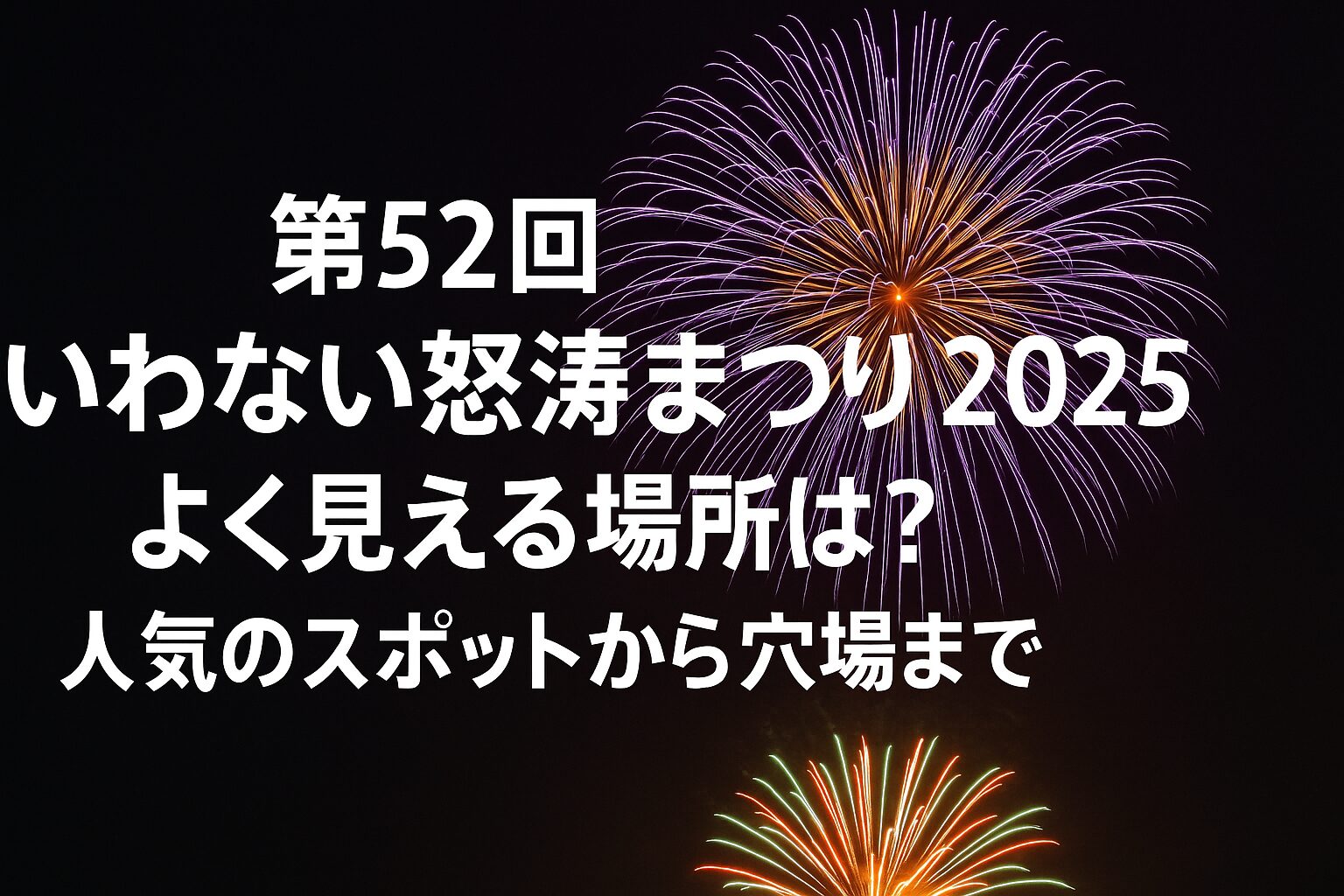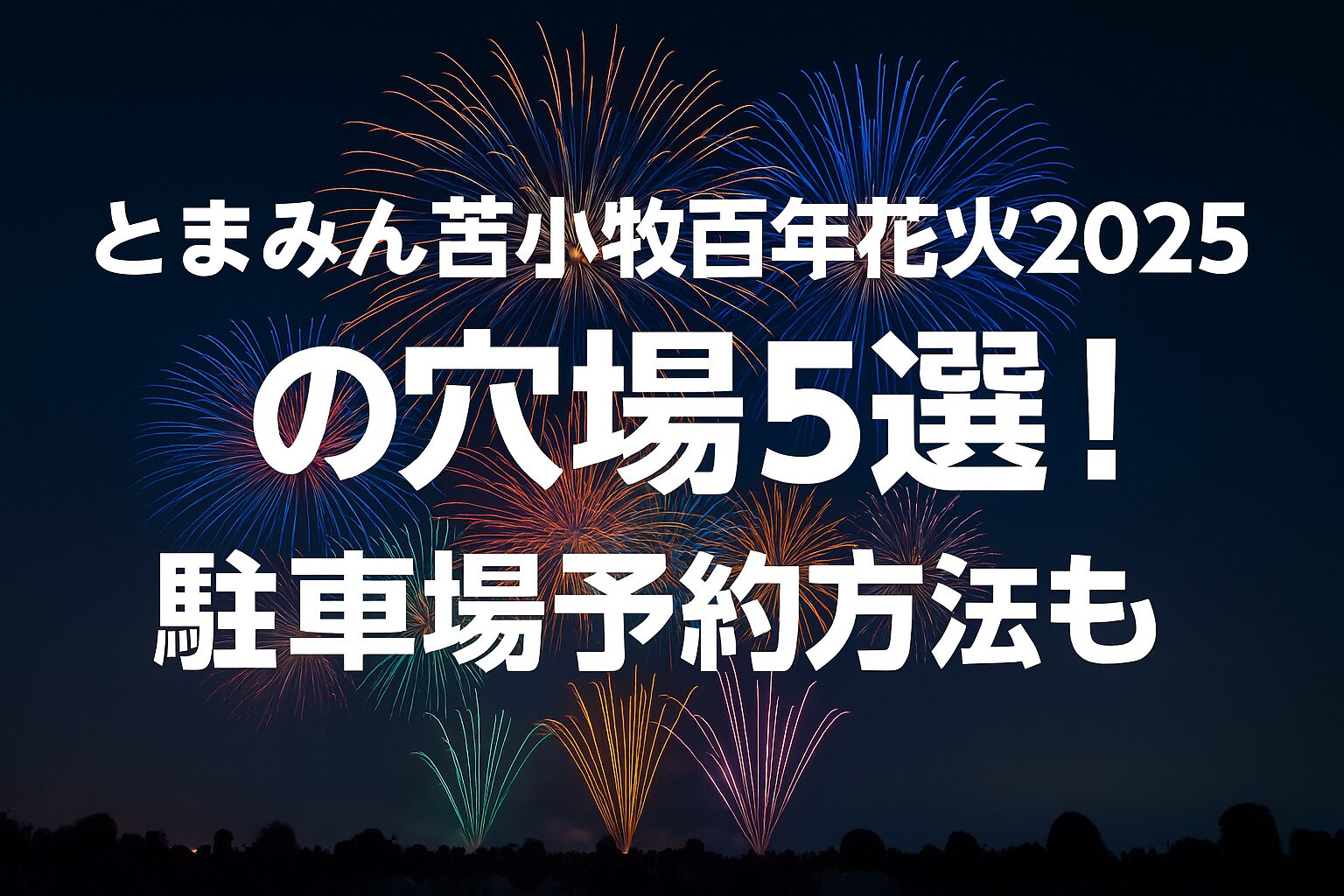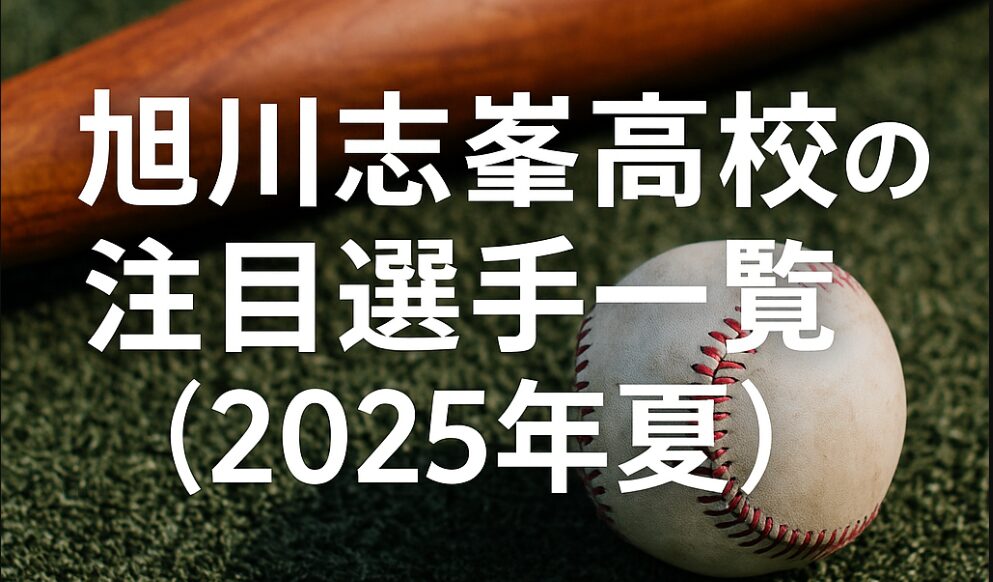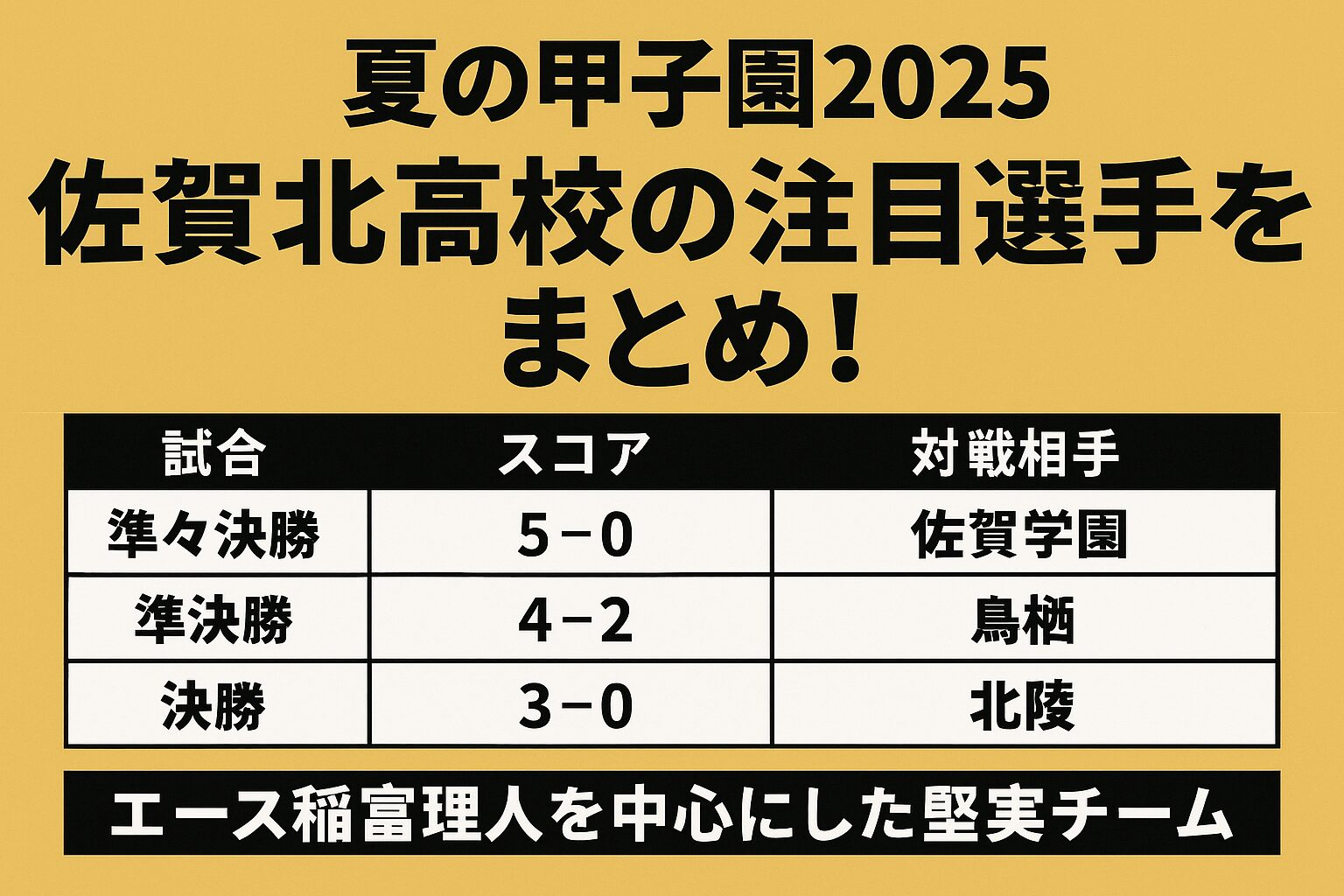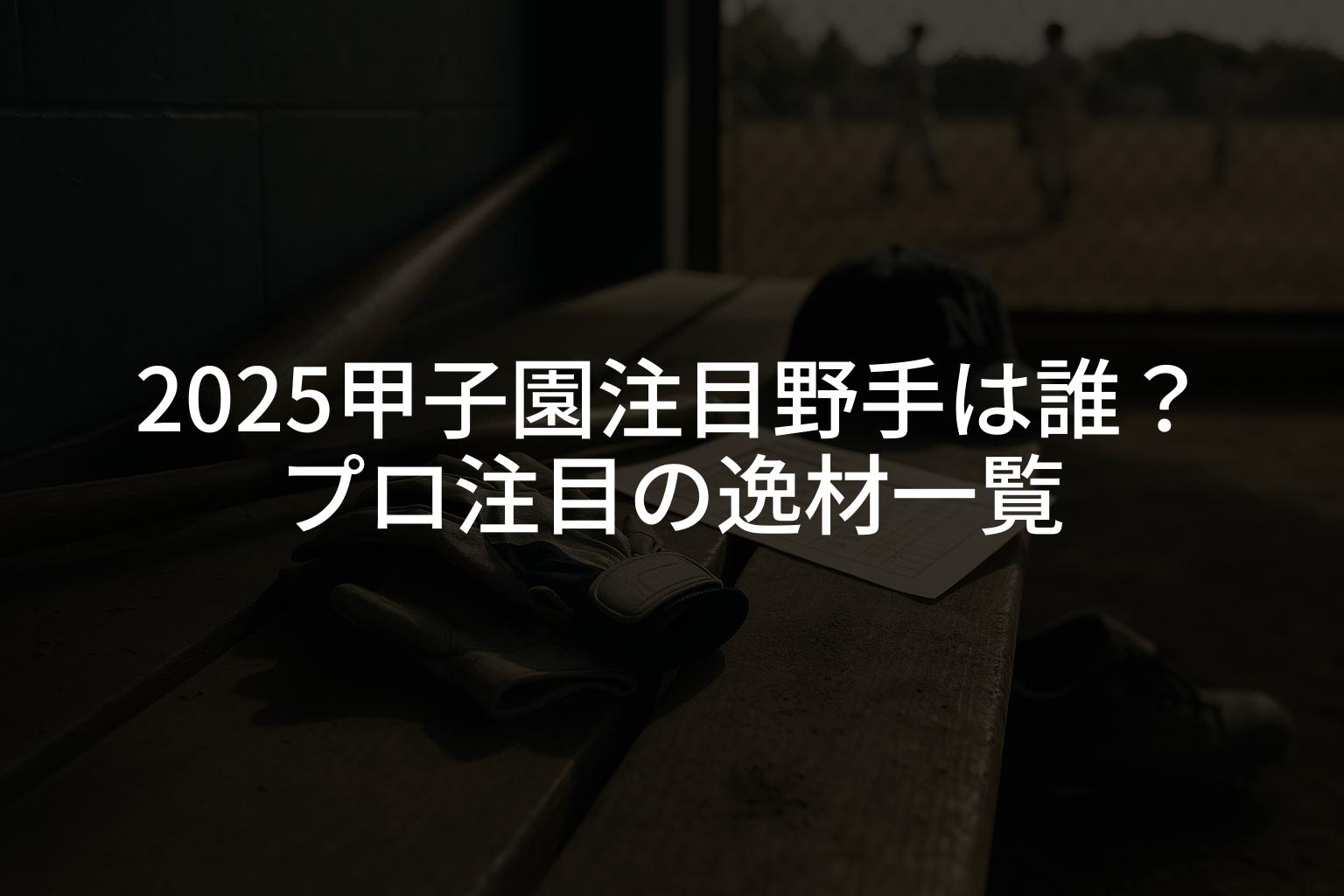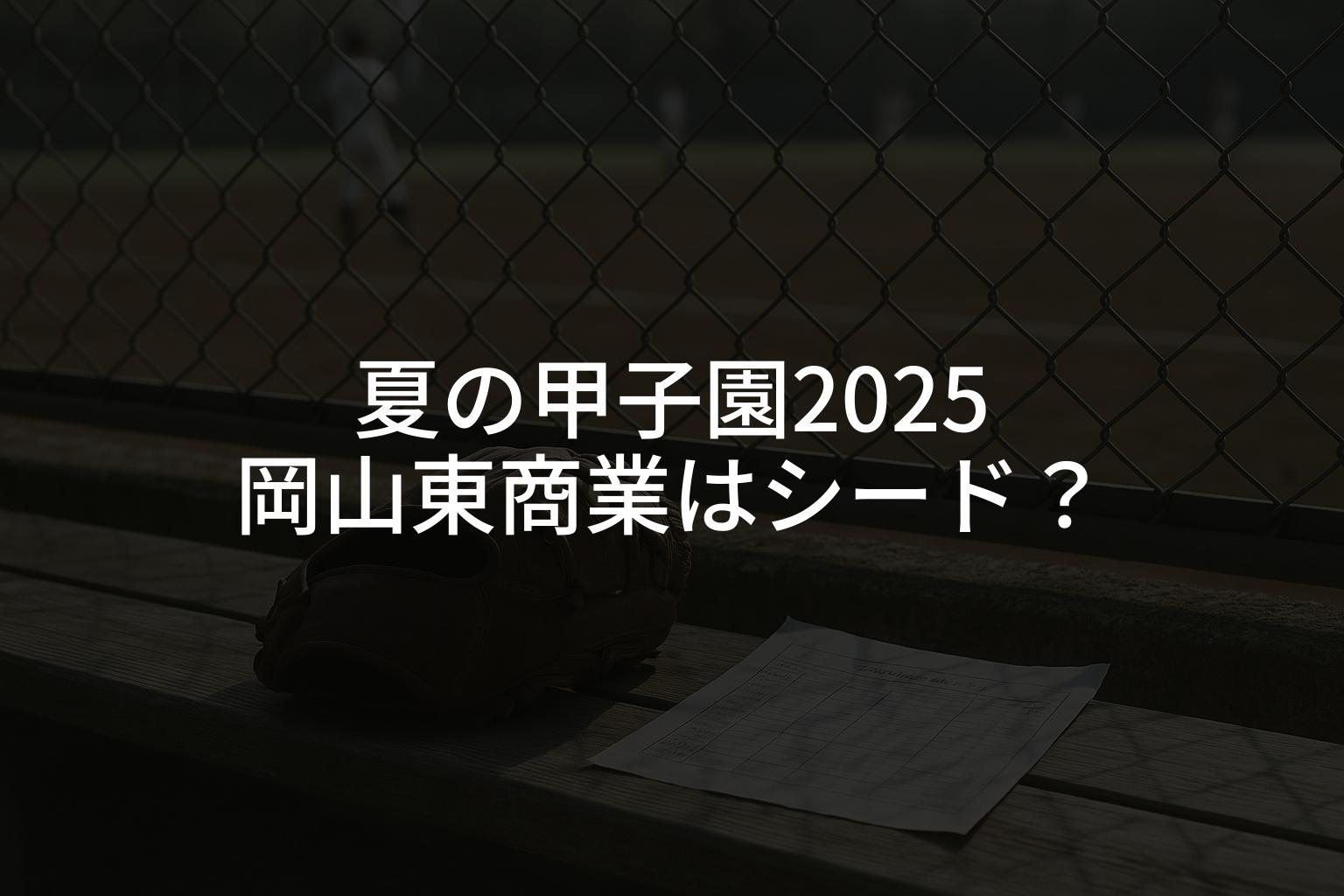2025年8月1日から、これまで私たちが当たり前のように使っていた「紙の保険証」および「プラスチックの保険証」が原則として廃止され、マイナンバーカード(通称:マイナ保険証)への一本化が進みます。
すでに政府から公式に発表されており、医療機関や薬局でも順次対応が進んでいます。
しかしながら、まだ多くの人にとって「マイナ保険証ってどうやって使うの?」「本当に紙の保険証がなくなるの?」といった疑問や不安が残っているのも事実です。
本記事では、廃止の背景から利用上の注意点、移行に向けて今から準備すべきことまで、徹底的にわかりやすく解説します。
紙の保険証・プラスチックの保険証は2025年8月1日に原則廃止
2025年8月1日より、現行の健康保険証(紙・プラスチックカード)は原則として廃止され、マイナンバーカードと一体化された「マイナ保険証」への一本化が正式に開始されます。
これは「デジタル庁」および「厚生労働省」が推進している医療DX(デジタル・トランスフォーメーション)の一環で、医療現場の効率化と国民の利便性向上を目的としています。
したがって、2025年8月以降は病院や薬局の受付で、紙の保険証を提示しても原則使用できなくなります。
ただし、一定の経過措置期間として「資格確認書」が交付され、マイナンバーカードを持たない人も医療サービスを受けられるよう配慮されます。
紙の保険証廃止の背景と目的とは?
紙の保険証廃止の背景には、行政手続きのデジタル化の推進があります。従来の紙の保険証では、保険者ごとの発行や紛失対応、更新管理などに多大なコストと手間がかかっていました。
それに対し、マイナ保険証ではオンラインでの資格確認が可能になるため、事務処理の迅速化や、重複医療の防止などの効果が期待されています。
また、災害時や転職時にもスムーズに保険情報を確認できるなど、利便性の高さが評価されています。
とはいえ、マイナカードの取得率や使用率が未だ低いこともあり、全国的な理解と周知が課題となっています。
紙の保険証が廃止されることで生じる影響
では、実際に紙の保険証がなくなることで、私たちの日常にはどのような影響があるのでしょうか。最大の影響は、マイナンバーカードがないと病院での受診が難しくなる点です。
もちろん資格確認書を申請すれば対応可能ですが、手続きや有効期限の管理が面倒と感じる人も多いでしょう。
また、高齢者や子ども、障がいを持つ方など、マイナカードの取得が難しいケースでは、医療現場に混乱が起こる可能性も懸念されています。
そのため、家族単位でのサポート体制や、各自治体の対応策にも注目が集まっています。
マイナ保険証に移行するには?準備すべきこと
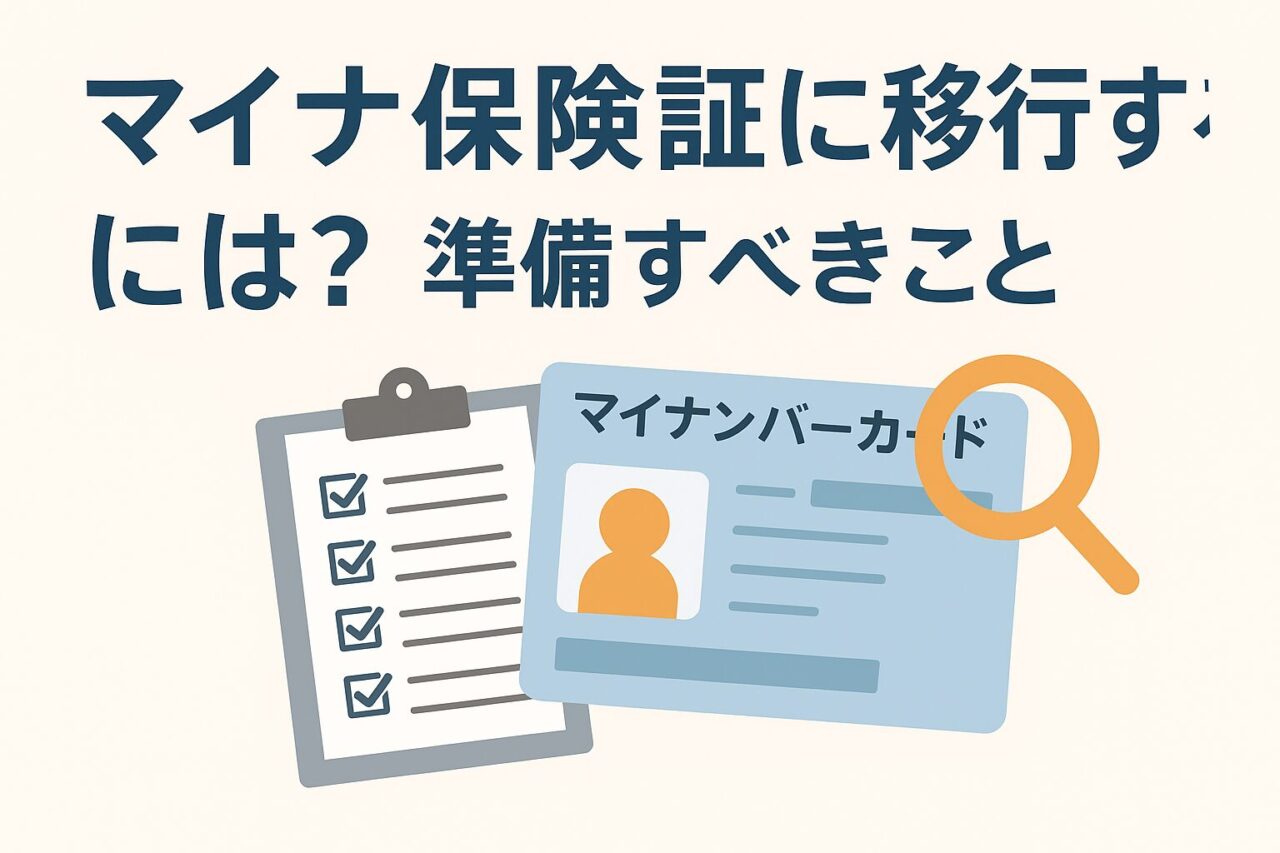
今からできる準備として、まずはマイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用申込を行う必要があります。
これは「マイナポータル」やコンビニの端末、または市区町村の窓口などで対応可能です。申し込みを済ませることで、マイナカードが保険証として使えるようになります。
さらに、医療機関によってはまだマイナ保険証に対応していない場合もあるため、受診予定の病院やクリニックが対応済みかどうかを事前に確認しておくと安心です。
高齢者・子ども・障がい者への影響と対応策
マイナ保険証への移行において特に心配されているのが、高齢者や子ども、障がい者などのいわゆる「情報弱者」層です。これらの人々がマイナンバーカードを取得できなかったり、操作に困るケースは珍しくありません。
そこで政府は、2025年8月以降も「資格確認書」の交付を通じて、こうした人々の医療アクセスを保障するとしています。
また、介護施設や保育所、福祉施設などでも支援体制の整備が進められており、自治体によっては出張申請サービスなどの取り組みも始まっています。移行期間中はこうした地域サービスを活用することが推奨されます。
まとめ
2025年8月1日から、紙およびプラスチックの健康保険証が原則廃止され、マイナ保険証への完全移行が始まります。
背景には医療の効率化とデジタル化の推進があり、今後はマイナンバーカードの取得と活用が必須となります。とはいえ、まだ対応できない方々への配慮も設けられており、「資格確認書」の発行や自治体の支援策が用意されています。
今からできる準備としては、マイナンバーカードの取得と利用申請が最優先です。また、受診予定の病院がマイナ保険証に対応しているか確認しておくことも重要です。
制度変更に柔軟に対応できるよう、情報をこまめに確認し、安心して医療を受けられるよう準備を進めていきましょう。